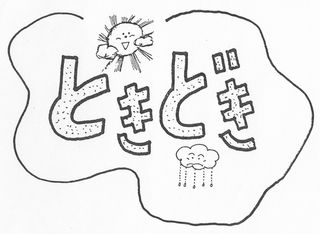「横山あげんだい」と書かれていますが、この地域の祭りに使われる松明(たいまつ)のようなものでした。上の籠に小さい松明を投げ入れて早く火が付くのを競う祭りだそうです。火の付いた玉入れですよね。すごいな(^^;) 岡部宿は山間の宿場で柏屋(かしわや)という旅籠(はたご)の様子が展示されていて興味深かったです。旅の疲れを癒(い)やす方法は昔も今も変わらない気がします。


そこからは遅い時間に山道となり水もなく少し心細かったです。間宿(あいのしゅく)宇津ノ谷(うつのや)に出るとほっとしました。


日本紅茶発祥(はっしょう)の地、丸子宿を過ぎ以前寄ったとろろ汁の丁子屋(ちょうじや)まで来ました。戦国時代に創業したという丁子屋は自然薯(じねんじょ-山いも)に特製の味噌を入れ、削り節、玉子で味付けしたとろろ汁をご飯にかけていただきます。美味しく身体にやさしいです。

でも今日はさすがに疲れて寄らずに足取り重く安倍川駅へ向かうのでした。