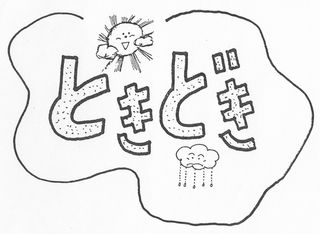さあ東海道の難所、大井川に出ました。「箱根八里は馬でも越すが 越すに越されぬ大井川」とうたわれた川です。現在はダムなどもあり水位の調節もできますが、当時は水量も多く、雨が降ると川止めで渡ることができませんでした。

そのため川を渡るには川越人夫(かわごえにんぷ)による渡河(とか)が必要でした。


お金もかかります。大井川の渡しは川の深さによって料金が変わります。股下で48文(1440円)腰で68文(2040円)脇下で94文(2820円)です。図のような連台はさらに高くつきました。

何日も雨が降ると川の両側の渡し場近くの宿場に泊まり続けなければならず、渡る順番を決める川会所の役人もいました。

島田宿には大井天満宮があります。大井川の氾濫(はんらん)に悩まされた宿場の人たちが守護のために建立(こんりゅう)しました。天満宮で変わった像を見ました。鹿島踊りというものだそうです。出で立ちがすごいです。

昔島田に嫁いできた花嫁が晴れ着姿を宿場内に披露していましたが、花嫁の大変さもあり、いつしか帯を大奴(おおやっこ)が木の刀の柄にさげて披露するようになったとのことです。そのことで良い帯を求める人々や商人が集まりファッションショーのようなお祭りとなりました。
いろいろな物語がありますね。