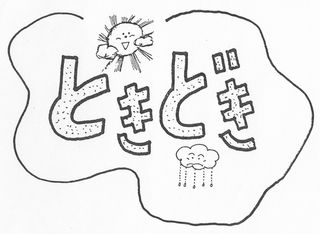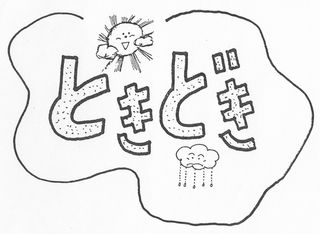木曽路は湧き水が豊富で至る所に共同の水場があるのでした。また道祖神や地蔵が多く置かれ信仰心とともに旅の大変さが感じられました。

贄川(にえかわ)では関所が人が通りにくい険(けわ)しい谷間にありました。旅人はどうしてもここを通過しなくてはならなかったのですね。

木曽平沢町では漆器(しっき)の店が道の両側にずらりと並んでいて、地元の豊富な木材や漆(うるし)を使った産業がここで生まれたのだと思いました。私はここで漆器のカップをお土産に買いました。


今日は4万歩、少し歩きすぎました。奈良井(ならい)の宿に到着して電車を待つ間宿場を見学しながら蕎麦(そば)を食べたり珈琲を飲んで過ごしました。当時の様子がよく残されている宿場でした。






NO.15
塩尻宿~ 奈良井宿
H21.7.4 約21km
これより木曽路
 塩尻を出発してしばらくすると平出(ひらいで)遺跡があり、見学したところ出会った人にいろいろ教えて頂けました。遺跡の竪穴(たてあな)式住居跡も復元されていて以前は多くの人々が訪れた場所とのこと。葡萄(ぶどう)の実も青々として初夏の風情(ふぜい)でした。
塩尻を出発してしばらくすると平出(ひらいで)遺跡があり、見学したところ出会った人にいろいろ教えて頂けました。遺跡の竪穴(たてあな)式住居跡も復元されていて以前は多くの人々が訪れた場所とのこと。葡萄(ぶどう)の実も青々として初夏の風情(ふぜい)でした。


道は洗馬(せば)宿で善光寺道と道を分けます。本山(もとやま)宿を過ぎるとこれより木曽路の道標が立ちいよいよ木曽の道中となります。道路から離れ山の中を歩く道にも出会いました。