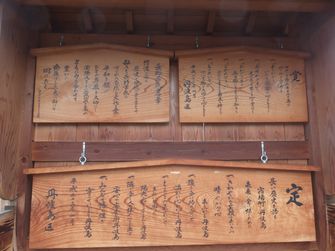H29.7.25 約19km
千曲川

2日目は時々雨の降る中での歩きとなりました。屋代駅を立つとすぐに立派な一里塚碑がありました。大きな石に一里塚の文字が刻まれています。

須須岐水(すすきみず)神社では茅輪(ちのわ)祭のぼりが立ちこの茅輪をくぐって参拝します。この行事は日本各地で行われていて街道歩きの神社ではよく見かけます。母の体内には神通力があるのですね。

千曲川を渡ります。昔は矢代の渡し場がありました。川を渡ることは橋の無い時代には命にも関わる大変なことだったのでしょう。今、千曲川を見て自分で渡って下さいと言われたら本当に困ると思います。

信州名物りんごの実が青く大きくなっています。赤くたわわに実るのが楽しみですね。

篠ノ井追分宿の碑です。昔の姿はありませんが追分という地理からも活気ある宿場であったようです。