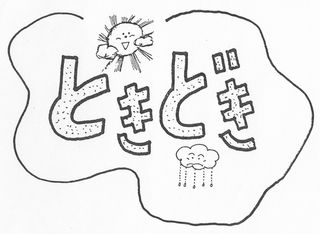桑名(くわな)市に入ると矢田の火の見櫓(ひのみやぐら)がありました。江戸時代は火災を恐れることは現代よりも数倍も恐怖が大きかったことでしょう。この半鐘(はんしょう)が鳴ることがなければ良かったのですが。

桑名の港に着きました。東海道はここから船での渡しとなります。小さな舟で天候にも左右される渡しは東海道の難所でした。


桑名の焼きハマグリという言葉は有名ですが、最近では天然物はとても少なく高級料亭でしか食べられないそうです。残念。


ここから先は大きな川が何本も流れ込むため船で海岸沿いに進むことが必要だったのでしょう。もっと昔はどうしてたのかな?