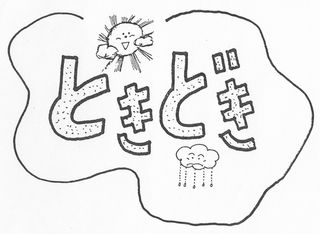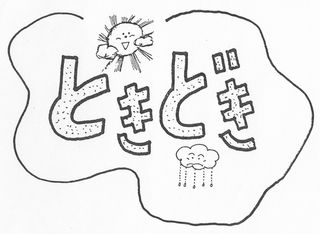中冨田(なかとみた)一里塚の碑がありました。江戸時代主要街道の両側に一里(4km)ごとに作られた塚で距離を確認できるものでした。ここの塚は無くなっているようでした。

庄野宿に入りました。このように標識があると分かりやすいですね。

また一里塚が現れました。もう一里を歩いたのでしょうか。ここは石薬師(いしやくし)宿の一里塚です。

石薬師宿には日本の唱歌-夏は来ぬ-「卯(う)の花の匂(にお)う垣根にほととぎすはやも来鳴きてしのびねもらす夏は来ぬ」の作詞、佐々木信綱(のぶつな)の生家と記念館があり、時間ぎりぎりでしたが見学させてもらいました。

その庭には卯の花が植えられていました。残念ながら花は見られませんでしたが「うつぎ」という名前だそうです。

佐々木信綱氏の書斎です。

この日は東海道の急坂、杖衝坂(つえつきざか)を下りました。京都からは下りになるのでほっとしますが登るときには杖をつきたくなるような坂でした。





NO.5 H17.9.24
関宿~石薬師宿 約23km
一里塚と杖衝坂

昔が偲(しの)ばれる様子が残されている関宿から出発です。

関の小萬(おまん)のもたれ松の碑がありました。江戸中期に夫の仇討ち旅に出た女性がここで子を産んで死に、その子が成人して仇討ちを果たしたことに関わる松だそうです。本当に仇討ちがあったのですね。それに執念(しゅうねん)深い。(-_-;)

秋の気配が感じられて彼岸花がきれいです。

道は川沿いに出ました。山を抜けた気楽さがありのんびり歩きました。

石上寺では講が開かれていました。多くの人が熱心にお坊さんの経に合唱していたのが印象的でした。