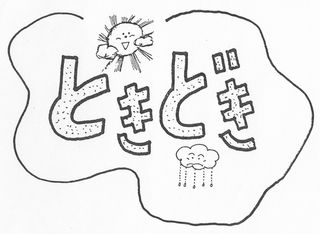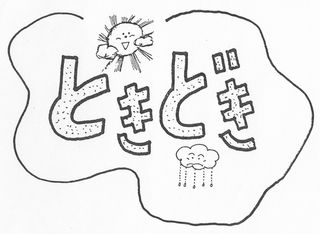地図および歩行距離は大まかなものです。見学等で距離が長く表示されます。
亀の水不動尊がありました。亀の口から清水が出ていたので飲ませて頂きました。昔もきっと大切な水場だったと思います。
 山科(やましな)区に天智天皇陵(てんちてんのうりょう)があります。初めてなので寄ってみました。長く続く参道を行った先に深い山に囲われて天皇陵がありました。
山科(やましな)区に天智天皇陵(てんちてんのうりょう)があります。初めてなので寄ってみました。長く続く参道を行った先に深い山に囲われて天皇陵がありました。


山科地蔵 徳林庵(とくりんあん)に寄ります。京都主要街道に設置された六地蔵の一つとして霊験あらたかとのことでした。

「これやこの行くも帰るも別れては 知るも知らぬも逢坂(おうさか)の関」と百人一首に読まれた逢坂の関を越えます。人が出会う交通の要衝(ようしょう)だったのですね。

蝉丸(せみまる)神社上社の石段も登ってみました。蝉丸は平安初期の歌人で盲目の琵琶法師(びわほうし)であったとのことです。

次々に有名な名前に出会います。ここは義仲寺(ぎちゅうじ)。木曽義仲(きそよしなか)の死後、巴御前(ともえごぜん)が日々供養(くよう)したと伝えられています。木曽に居たら二人で幸せに暮らしたのでしょうか。

瀬田の唐橋(せたのからはし)に着きました。京都防衛のための交通の要衝にあるこの橋は数々の戦いのたびに焼き落とされ、そのつど架け直されたそうです。





NO.1 H17.5.23
京都三条~瀬田唐橋 約20km
蹴上の坂

京都三条大橋が東海道の起点です。弥次さん喜多さんの像に見送られていよいよ橋を渡り出発します。


渡り終えるとそこに高山彦九郎の像がありました。江戸時代後期の熱心な勤王思想家で全国を遊説(ゆうぜい)したそうです。京への出入りの際にはこの像のように皇居に向かって礼をしたそうです。勤王の活動を行っていたところ、九州で幕府に捕縛(ほばく)され自刃(じじん)しました。

京都への名残(なごり)のため後ろ髪を引かれる思いで蹴上(けあげ)の坂を登ります。京を立った旅人は足取り重く登ったことでしょう。

東海道の難所だった日ノ岡から蹴上にかけての峠には轍(わだち)をつけた石(車石)が敷かれていました。荷車を通りやすいようにしたものです。その様子が展示されていました。

東海道の古道は狭い道が続きます。