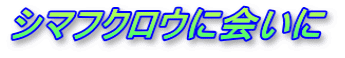翌日は海に出てトドを探しました。羅臼のトドは漁師さん達にとって魚を減らしてしまう害獣です。この日は駆除のボートが出ていてトドの姿はなかなか見られませんでした。遠く一部姿が見られただけとなってしまいました。観光と漁業、難しいですね。

でも観光船から魚を投げると集まっていたオオワシが海から魚を捕まえていきます。その姿は力強く美しさも感じられる自然の姿でした。

船を降りツアーは野付半島に向かいました。半島に着くと本土と半島に囲まれた内海が凍っていて積もった雪の上には動物の足跡が見られます。バスがスピードを落としました。するとすぐ近くにエゾシカが草を食んでいます。枯れた草原では十分な食事にならないだろうと心配しました。厳しい環境の中で生きることは大変です。
半島の先に着くとネイチャーセンターがありました。センター内には動植物のパネルなど素敵なものが展示されています。見学を終えて外に出るとそこにはキタキツネがいるではありませんか。人慣れしていることもあるのでしょうが、会えて嬉しかったです。

ツアーの最後に丹頂(タンチョウ)の里、鶴居村鶴見台へ行きました。タンチョウはロシア、中国から越冬のために飛来します。乱獲や生息地の激減で数を減らし大正時代には全く姿が見られませんでした。そのため1924年に釧路湿原で再発見されるまでは絶滅したと思われていました。

鶴居村では酪農の牧場に少数が飛来したことから保護に尽力した伊藤良孝さんをはじめ村の人達がトウモロコシなどを分け与え給餌をしたそうです。その甲斐もあり、さらに北海道庁の協力もあって数を少しづつ回復しました。2020年現在では1900羽が確認されています。
野生動物は出会うことが難しいこともありますが、そこに生息していると感じるだけでほっとしたり嬉しかったりもします。人と共存できる環境がいつまでも続くといいですね。