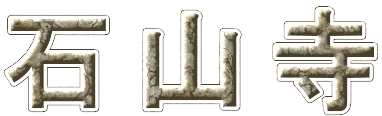

石山寺は琵琶湖の南端近くに位置し、琵琶湖から流れ出る唯一の瀬田川の右岸にあります。瀬田川は宇治市の天ヶ瀬ダムから宇治川と名称を変え、京都府と大阪府の境で桂川、木津川と合流し淀川となって大阪湾に注ぎます。。
石山寺の開基は天平19年(747年)良弁僧正によります。天然記念物の石山寺硅灰石(けいかいせき)という巨大な岩盤の上に本堂などが建てられている東寺真言宗の大本山の寺院です。令和3年(2021年)長い歴史で初めての女性座主、鷲尾龍華座主が誕生したそうです。
今年のNHKの大河ドラマ「光る君へ」の主人公、紫式部がここで「源氏物語」の着想を得たとされていて、本堂の合の間には「紫式部の間」もあります。他にも平安時代に書かれた「枕草子(まくらのそうし)」「蜻蛉(かげろう)日記」「更級(さらしな)日記」にも石山寺の名が登場するなど平安文学と深い関わりがありました。日本には古くから活躍する女性作家がいたのですね。大河ドラマにより興味を持った石山寺ですが、テレビの影響はすごいですね。(^^;)


「急がば回れ」ということわざは聞いたことがあるかも知れません。草津宿に近い矢橋港から大津港まで舟で行く東海道の短縮コースとして使用され、唐橋回りの半分ほどの時間ですみました。ちなみに私は4時間ほどかけて歩きました。でも冬から春は風が強く舟が欠航となることもあったそうでやはり「急がば回れ」だったのでしょう。
その大津港にほど近い所に明治時代、琵琶湖疎水(そすい)が作られました。滋賀県大津市から京都府京都市へ琵琶湖の水を流すために使用された水路です。京都の蹴上げには水力発電所がありますが、この琵琶湖の水が使われていました。現在でも琵琶湖の水は京都になくてはならないものですが、近年琵琶湖の水量が減って大きな問題になりました。
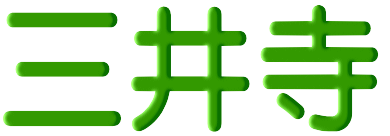

三井寺は天台寺門宗の総本山としてあります。歴史は古く670年頃、飛鳥から近江大津に都が移されたことが契機となり寺が建立されました。当初は園城寺と呼ばれていましたが、その後天皇の産湯に用いられた霊泉のあることから御井の寺、三井寺と名称が変わりました。境内は広く国宝の金堂をはじめ、重要文化財がたくさん残っています。一通り見て歩くだけでも1時間はかかってしまいました。


最近新しい観光スポットとして注目を浴びています。ロープウェイで登った1108mの打見山々頂にあるテラスでは琵琶湖を一望でき、そこにあるカフェで珈琲を飲みながらゆったりとして素敵な時間を過ごすことができました。
隣の蓬莱山はスキーも楽しめるので外国人観光客の皆さんがたくさん来ていました。琵琶湖西岸は雄琴温泉もありますが、観光では少しひかえめな気がします。それでも近江大橋付近の浮御堂や中央部の白鬚神社が見学地としてありました。


琵琶湖周航の歌
瑠璃の花園 珊瑚の宮
古い伝えの 竹生島
仏の御手に抱かれて
ねむれ乙女子 やすらけく
と歌われた竹生島(ちくぶじま)には是非行ってみたいと思っていました。
琵琶湖北部の無人島で琵琶湖では2番目の大きさになります。島には宝厳寺(ほうごんじ)、竹生島神社があり観光の中心となっています。神亀元年(724年)聖武(しょうむ)天皇が夢枕に立った天照皇大神(あまてらすおおみかみ)の言葉により建立されました。平和で豊かな世界が造られるとのお告げでした。
竹生島には船で渡ります。島の上に続く階段は少しきついですが、登ると山上には本堂や三重塔があります。また豊臣秀頼が京都から移築した唐門は国宝に指定されています。令和に入り屋根の葺き替えや塗装の修復など行われ、きれいになったそうです。とても神秘的な雰囲気のある竹生島でした。











