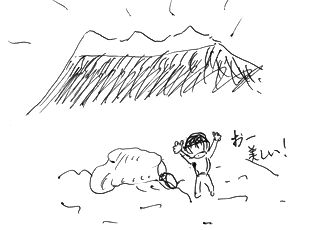しかしラッセルは深く、コース探しも時間がかかり、一番大変な斜面を横切る頃には夕方になってしまいました。パーティーが斜面の中程にさしかかった時に2年生の中に疲労で行動が遅くなってしまう者が出てしまいました。
かなり難しい状況となり私達は行動の中止を決めました。吹雪の吹き荒れる中、樹木の無い山の斜面でテント張りはできません。テントを降ろすと一人一人その中に潜り込みます。荷物も入れるとテントの中はいっぱいです。ザックの上に座り、背中でテントを支えるような状況です。
疲れてしまった2年生に非常食を食べさせ、シュラフの中に入れて寝かせました。3年は横になるスペースもないので一晩中ラジウス(石油コンロ)を膝の上で炊いて過ごしました。居眠りをしていた3年の仲間がコンロを落としみんなで大慌てで消したという事件もありました。
やがて外が明るくなってきました。風もやみもう大丈夫でした。しばらくしてテントの外に出た我々の前に山頂部が朝日に輝くモルゲンロートが見られました。その美しさは今までに見たこともないものでした。そして山の斜面を下った森の中には山小屋の屋根が見えているのでした。あとちょっとだったんだけどなあ。冷たく白くなってしまった手の指先を温めながらため息をつく私でした。
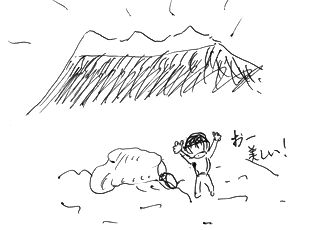
そんな4年間を共に過ごした仲間は卒業後も合宿を続けています。当初は八ヶ岳全山縦走なども行っていたのですが、最近は旅館で温泉に入り麻雀をやり、パターゴルフや釣りなどを楽しむ合宿と変わってしまいましたが。(^_^;)
私はこのワンゲルとの出会い以後、自分で計画を立てその計画を実行していくことに楽しさを感じるようになりました。この出会いは自分の視野を広げ、たくさんの出会いを生んでくれることにもなりました。

ワンゲルの仲間
2年生になると新入生の指導が任されます。先頭に立ってトレーニングをしたり、自分達が教えられてきた知識を後輩に伝えます。また各合宿やパートワンデリングでのリーダーを務め、企画から運営まで責任も大きくなっていきました。
しかし新入生が合宿でバテると大変です。自分の荷物と1年生の荷物を持って山を登らなくてはなりません。50kgは越えている荷物は背負うのも大変だし、ひざに大きな負担がかかりガクガクする事もありました。それでも合宿中には余裕が有り、景色を楽しんだり仲間との話に花を咲かせました。
この頃になると自信のついたことで自分達で自由に山に行きたいと考えるようになり、部活動に縛られない山行を希望する者が出てきます。当然先輩達との考え方に合わない点が出てきてしまい、最終的にはワンダーフォーゲル部を退部する者が出てきてしまいました。先輩達ともずいぶん議論もし引き留めもされましたが残念ながら話し合いは決裂してしまいました。ずいぶん少ない人数となって不安を感じたものです。
やがて残った者は3年生となり多くの山行を企画、運営して自分達の思う計画ができるようになりました。その一年間も終了となる頃のリーダー錬成合宿でのことです。この合宿は2年生の力を高めるために行われ、1年生は参加しません。冬山で行われる合宿は企画から準備、実際の行動中のコース選定やラッセルなどみんな2年生に任せます。私達3年生はこのパーティーの後を着いていき山行の状況から必要時にアドバイスをします。
この年は例年より雪が多くて山に入ってすぐからコース取りに難しさを感じました。当然ラッセルも大変で、なかなか思うようには進みません。いつものテント設営地にたどり着くのが遅くなりました。翌日は少し早めの出発も検討されました。朝を迎え今日は少し大変な山の斜面を越えて山小屋までの行程です。しかし相変わらず雪が多く道探しに時間がかかってしまいました。
このままだと山小屋まで行けるかぎりぎりの時間になりました。2年生達は集まって相談します。明日は停滞日といって行動がない休息の予定でした。そのこともありなんとか遅くなっても今日は無理をしてでも行こうと結論をだしました。私達3年生も行けるだろうという判断をしました。


養成合宿が近くなるとテントを立てる講習会や安全な登山を行うため天気図や地図の見方、緊急時の対処の仕方、その他食事を作る訓練、先輩方に食事を配膳する順番などいろいろなことを学びました。登山用の装備も東京まで購入しに行き準備をしました。
いよいよ合宿が始まりました。バスに乗り丹沢山系の山に入ります。その日は登山はなくキャンプ設営や食事の準備に追われました。初めてのことなのでなかなかうまくいかないことも多く、先輩からは叱咤激励の声が飛び交いました。ようやく夕食となりましたが先輩からはとにかく食えと腹一杯のご飯を食べさせられ、食後食器を洗うときには吐かないように上を向いて洗うようでした。

翌日は起床から食事、荷物の撤収などを1時間以内に行うよう指示されましたが時間はオーバーして怒られます。出発すると大きな荷物を背負い列を作って山に登るのですが暑いし、昨日テントの中でよく眠れなかった疲れもあり、新入生はみな大変です。先輩の軽い荷物が恨めしかった。1時間程度歩いて10分の休憩を繰り返し山頂に着いたときには歓迎ワンデリングで感じた爽やかさや景色など見る余裕もありませんでした。
昼食は乾パンにソーセージ、粉末ジュースと以前とは雲泥の違いです。下山するとテント設営、食事の準備に追われ自然を楽しむという説明は一体どこに行ったんだろうと考えてしまいました。翌日の朝大学に戻るとそのまま授業に向かいます。実技授業はいいのですが座学は居眠りもしてしまうのでした
ワンゲルの合宿は1年間に7回ほど企画されます。2度の養成合宿を終えると夏合宿が行われます。長い期間の合宿なので荷物も重く、準備も大変でした。この年は北海道積丹半島や下北半島で行われましたが、毎回合宿地は変わります。
そしてその合宿が終わると山小屋の管理のための合宿、秋合宿、12月には1年間の総仕上げと冬山の準備となるリーダー錬成合宿、3月には5mもの積雪の山を行動する春合宿が行われました。その他個人や数名の有志パーティーで企画するワンデリングもあり多い人では10回以上も山に入るのでした。
12月にもなると新入生はいつの間にか人数が減っていきます。上級生になるにあたりリーダーとしての知識も必要となります。日赤の救急法講習を夜間東京まで出向き、1週間ぐらいかかって適任証の交付を受けたのもこの頃でした。
自分達で山行を計画するときには部内の企画委員会で検討されます。日程、コース、食糧、費用、避難経路、医療機関、天候対策等細かなところまで検討され何度も計画作成のやり直しを命じられました。こうして新入生は力を付けていき、先輩に指示されなくても一人でやっていける力をつけて上級生になっていくのです。

S63(1988).11
ワンゲルとの出会い
昭和49年(1974年)大学に入学した私は自分が入るべき部活動を見学に行きました。初めに体操部を見学しました。体育館では多くの学生がたくさんの器具の中で練習しています。こんなにたくさんの人や器具の中で練習したことの無い私は少し圧倒されてしまいました。
説明では体操部の1年生は入寮して合宿生活を行うと話がありました。私は困りました。入寮の費用を父母にお願いすることが難しかったからです。私の父は電気店を経営することが夢で、私にはその方面の学科を出て欲しいと願っていました。ところが私は自分の希望する体育学部へ進学したため父の夢を叶えられなくなってしまったのです。私は体操部への入部をあきらめました。
そこで何もせず大学生活を過ごすのも物足りないので他の部活を見学に行きました。いくつかの部をまわった後、ワンダーフォーゲルという名前に出会いました。名前の意味が分からず勧誘の説明を聞いていると自然の中でキャンプ生活などをして自然の知識や仲間との繋がりを広げていく部活動だと分かりました。山へ行く時以外は日常走ったり体力作りのトレーニングをして、アルバイトも可能だとのことです。
自然も好きだし、仲間が増えることは大切な事だと考え数日後入部を決めました。体育学部の学生がこの部活に入ってくることは珍しいそうですが、この年は2名が入りました。全員で14名の新入生でした。
4月の終わりに新入生歓迎ワンデリングがあり、近くの丹沢大山国定公園の中にある大山にハイキングに行きました。1年生は軽い荷物で山頂では上級生がお昼の飲み物を作ってくれ、天気も爽やかで景色も良く楽しい1日を過ごすことができました。こんな部活もいいなと私はワンゲルが好きになりました。しかし・・。

歓迎ムードもここまでで、いきなり近くの丘の上までのランニングや10階建ての校舎の階段を人を背負って登ること、腕立て腹筋、背筋などのトレーニングが始まりました。ある程度体力には自信があったので練習にはついて行けましたが結構きつかったです。
その上装備や石など50kgにもなるザックを背負い、10階の校舎の階段を上がったり校庭を全員で歩くなどのトレーニングが続きました。その頃マクドナルドの夜間清掃員のアルバイトを始めていた私は午後の授業など本当に眠かったです。